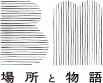[レポート] ダイアログ・オンサイトVol.1 「東京の記憶と断面」トーク後編
2019年1月9日に行われた東京ステイ「ダイアログ・オンサイト」トーク後編です。前編はこちらからどうぞ。
(取材・執筆:大間知賢哉、写真:黒羽政士)
ミナガワビレッジ / 街 / 暮らし/ 文化 再生の想像力
平成が終わり、年号をまたぐ変わり目に生きている中で、文化はどのように引き継がれるのか、とミナガワビレッジのヒストリーを参照しつつ、神本さんは問いかけます。

神本:戦後、参道のあたりは焼け野原になり、その後住宅街ができていく中で、そこがだんだんと商業エリアになって、そこに残された場所がミナガワビレッジだった。
持主の皆川さんが亡くなられて、甥っ子の三田さんが相続で引き継がれて。三田さんが不動産の方だったので、「若い世代の人たちが議論できたり、そういう場所って昔は表参道にたくさんあったんですよ」って話をされて。「よく鍋もしてたし、入居者たちが集まって、っていうのが表参道にもあったんです。ビジネスというよりも、そういう場所をまた取り戻してほしい。」と。

林千晶さんは、再生前の旧ミナガワビレッジを訪れたとき、当時下宿していた人たちの生活の残り香のようなものが、強烈に訴えかけてきたのを覚えているといいます。しばらく使われていなかった旧ミナガワビレッジを見たときに、リノベーション後の現在のような空間をイメージできなかったとのこと。だからこそミナガワビレッジの生まれ変わった姿に強く感動したようです。

神本 : 建築の用途が変わる瞬間みたいなものが重要になってきていると思うんですよ。もともと住宅として使われていたミナガワビレッジを再び住宅として改築するのでは、価値が担保できないから、オフィスビルの集合体になった。そういうときに、どう街としての文化を残しながら、エリアの価値を高め、熟成させていくことができるのか。

戦後の日本は、個人の自由を拡大し、風景は更新され続けてきました。その中で、消えてしまったものもあります。ただ、そんな以前の風景をそのまま再現することやある時点に戻そうとすることは必ずしも有効ではありません。そしてその場所の歴史を尊重しながらも風景を更新していこうとするならば、経済的な価値指標やかつてのルールだけで判断するのではなく、時代に合ったコンセンサスを形成するためのプロセスを組み込んでいく必要性がありそうです。
消えるまち、そこに残る地名と未来の文化
本日のテーマである「東京の記憶と断面」。過去の記憶と現在の風景が地層のように積み重なっているものの一例として、土地の名称が話題となりました。今はなき団地、小学校や寺院も、名前だけがその場所に残り続けています。昭和から平成にかけてのニュータウン構想。名前を付けること、そこにはブランディングの意思が働いています。良し悪しの問題とは別に、ある都市の歴史は、時代時代のそこに関わる人たちによって、価値付けられます。明治神宮へと延びる参道が、そのまま地域のエリアの名称になって、その後、人が行き交い、文化の発信地としての現在の表参道になりました。

都市開発の果て、何十年と経った先に、その文脈を知らない訪問者たちが、また新たにその土地を解釈し、意味付ける。若者がインスタグラムで発信するため、ロケーションに素材を求める行為は、場所をただ消費しているとの指摘もありつつ、その時の都市を写真・タグで刻印し、キャプションをつけ、拡散することで、そこにやって来た者たちのアーカイブが形成されているともいえるのではないでしょうか。
日本:平成~新元号、その断面。これからのまちは、自分たちで作れる?
これからのまちと私たちの関係性はどうなっていくのでしょうか。「いい意味でも、悪い意味でも、これからは私たち一人ひとりが頑張んなきゃいけない時代になりそうだな、自由が戻ってくるけど、責任も問われそう。」と林千晶さんは話します。

千晶:放置されてる自転車のたまり場、空き地みたいのがあって。そういう場所が増えていった時に、そこを自転車の置き場にしようってするのも、変えようっていうのも、なんか誰かにやってとか、誰かがダメって言って撤去する時代じゃなくて。私たちが嫌だからやめるのか、いいからやるのか。
捨てられた自転車は、またさらなる捨てられた自転車を引き寄せるけど、誰かが街の使い方を変えたら、それに引きずられて、真似されていく、そんな伝播がおこっていく。

千晶:もう行政がメンテナンスし、デベロッパーが作ってっていう領域が狭くなっていくから、どんどんみなさん自由にやっていいですよ、ただし、自分のお金でね、という時代になる。そういうことになることを次の世代の人たちは、それが責任とも気負わず、「まちって自分たちでつくるものですよね」っていう世代が生まれてくるのかなぁって。

その他にも、公共の力を借りずに、最新のタービンを導入した水車によるエネルギー生産でみんなが暮らしているというフィンランドの小さな村のお話が印象的でした。これは一例ですが、行政に任せるのではない、独自の新しい仕組み・構造が生まれ、自立していく方向にあります。地方の中心市街地問題、いわゆるスポンジ化がさらに進み、そのような場所がキャンバスになり、空き地・空き家をどう効果的に使おうかというマインドは、専門領域の人たち以外のところでもどんどん出てくるのかもしれません。その際にどんなツールを用いて、どのような暮らしをイメージし、デザインしていくのか、課題になりそうです。
フィクションと事実を行き来すること。
最後の質疑応答では、フィクションの可能性についての問いが、石神夏希さんから示されました。
石神 : リサーチなど事実検証をすることも大事だけれど、どこからどこまでが一体事実なんだろうかと思うんですよね。誰が語り伝えたか、それと厚見さんの想像力みたいなものを等価に扱うことはできないのかなぁって。
ほんとか嘘かは分からないけど、厚見さんがイメージしたヴァンナチュール系のチャイナを教えてくれたあの女性だっているかもしれないじゃん、きっとそうだよね、みたいなこと。

千晶 : 人間の中に事実とフィクションの差ってないと思っていて。私からすると、まるでそれは物語のよう。例えば、裁判を聴いてると事実ってないんだなぁって感じたことがあって。真逆の事をお互いが言い合って、こっちが真実、いや、こっちが真実って、私にはたぶん両方にとってそれが真実なんだろうなってくらい、世の中はフィクションしかない。
神本:最適化によって事実だけしか表に出ない世の中になっているけれども、あえてフィクションとかに目を向けることって大事なんだと思いますね。
厚見:まちづくり・都市計画の領域における今日の制度や考え方には、よろしくないことがたくさんあるし、みんなが徐々に気付き始めていることや、長期的には失われている価値がある。そういうものをよくしていこうって思った時、頼りになるのはロジックにもなりきれないところだったりもするから、心のスイッチをうまく入れていくしか変わらない部分があるんですよ。

時間をかけて、歩く。すると、目的地に向かうための移動ではないモードに。なんだかいつもと違う眼差しを獲得する。「ピルグリム」では、ここにいない誰かに宛てて手紙を書きます。ちょっぴり恥ずかしいけれど、私だけの小宇宙を作って、綴る。事実とフィクションに差はない。あるのは、誰かが生んだ物語、伝え聞いた物語、出会った物語。
「フィクションと事実を行き交う旅」。ピルグリムはそのための、ちょっとした手解きといえるかもしれません。